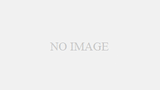源実朝は、鎌倉幕府第3代将軍。父は初代将軍・源頼朝、母は北条政子。兄の頼家が暗殺された後、第3代将軍になりますが、当時12歳だったため、実権は母の政子と政子の弟で第2代執権の北条義時が握りました。実朝は歌人としても知られ、自らの歌集『金槐和歌集』をまとめています。1218年、頼家の子、公暁によって鶴岡八幡宮で暗殺されます。
🔶源実朝ゆかりの地
鶴岡八幡宮
実朝が暗殺された場所。1219年、右大臣拝賀の式典後、階段を下りる途中で甥の公暁に襲われました。公暁が隠れていたという話がある鶴岡八幡宮の大銀杏は、2010年に倒れてしまいました。
若宮の東側には白旗神社があり、源頼朝・実朝が祀られています。
境内の鎌倉国宝館前には歌碑があり、「山はさけ うみはあせなむ 世なりとも 君にふた心 わがあらめやも」という『金魂和歌集』に収められている一首が刻まれています。使われている碑石は、もともとは関東大震災で倒壊した二の鳥居の柱です。
実朝歌碑・坂ノ下
鎌倉海浜公園(坂ノ下地区)にも源実朝の歌碑があります。小倉百人一首(第93番)に選ばれた「世の中は つねにもがもな なぎさこぐ あまの小舟の 綱手かなしも」が刻まれています。歌碑の台座は船を、歌碑板は帆を、手前は波をあらわしています。かつて大船を建造し、当時の中国(宋)に渡ろうとしていた実朝の夢を形にしています。
歌の橋
1213年、渋川刑部六郎兼守が謀反の罪で捕らえられたとき、無実を訴えるために和歌十首を詠み、荏柄天神社に奉納しました。源実朝はその和歌を見て感動し、その罪を許したため、兼守は死刑を免れました。そのお礼にと荏柄天神社の参道近くにこの橋を架けたので、この名がついたと言われています。
壽福寺
1200年、北条政子が頼朝の死後、頼朝の父である義朝の旧邸跡に栄西を招いて創建したお寺です。実朝もしばしば訪れ、最盛期には十数か所の塔頭を擁する大寺であったといいます。墓地の山側にはやぐらが二つ並び、一つは政子、一つは実朝の墓だといわれています。中にはともに供養の五輪塔があります。実朝のやぐらには唐草のような模様が見られるので「からくさやぐら」とか「絵かきやぐら」といわれます。